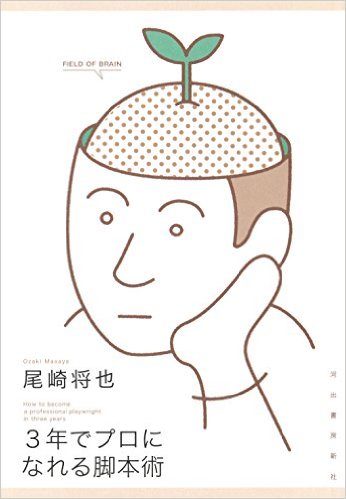先日、日本脚本家連盟の教室で、映画を分析する講義をしました。題材に選んだのは「ゴースト/ニューヨークの幻」。今回はこの講義で話したことのうちいくつかを紹介します。
「ゴースト/ニューヨークの幻」は90年に公開されたジェリー・ザッカー監督、パトリック・スウェイジ、デミ・ムーア主演の映画。これを講義の題材に選んだのは、非常によく出来たエンタテインメントで、面白くするためのテクニックが数多く使われているからです。以下に書くことは、この映画を見ていないと何のことかわからないので、まだ見たことのない人は見た上で読むことをお勧めします。
まず前にも書いた「物語を把握する」ということから。この映画は見終わった後の印象では、主人公の男女の愛を描いたロマンチックな映画という感じが強いです。しかし物語をよく見ると、「殺人が起こり、犯人を探して突き止め、犯人のさらなる悪事を阻止した上でやっつける」という「事件もの」の型を踏まえていることに気づきます。事件ものは普通なら刑事や探偵が主人公になって事件を解決しますが、この映画では殺された本人が幽霊になってその役割を果たすのがユニークなところです。そしてその物語をラブ・ロマンス的な要素でくるむことで、殺伐とした事件ものではなくロマンチックな映画という印象を観客に与えることに成功しています。
この作品は「カセ」を非常にうまく使っています。生きている人たちは幽霊になった主人公サムの存在を気づいてくれず、何かを知らせたくても手段がありません。また幽霊は物体をすり抜けてしまうので、物理的な作用を及ぼすことも出来ないのです。物語はサムがこのカセを克服しながら進みます。生きてる人とコミュニケーションを取るために、唯一コンタクトが取れる霊媒師のオダ・メイに頼むサムですが、恋人モリーはなかなかオダ・メイの言うことを信用しなかったり、せっかく一度信用してもオダ・メイの過去の犯罪記録を見てしまって信用が崩れたりと、次から次へとカセ(主人公が困ること)が押し寄せます。また主人公が頼りにする相手のオダ・メイや地下鉄の幽霊(物に触る方法を教えてもらう)が、単に親切な人ではなく、サムの頼みを断ろうとするところも、キャラの面白さになると同時に物語的なカセとして機能しています。
主人公の恋人・モリーは非常に「ヘタレ」なキャラとして描かれています。主体性というものがなく、恋人サムが死んでしまうとメソメソしているばかりで、あげくの果てにサムの友人カールに口説かれてキスされてしまったり。しかしモリーがもしこういうヘタレなキャラでなく、前向きにどんどん行動するキャラだとしたら、幽霊になった主人公のサムがやることがなくなってしまいます。サムが幽霊というカセを乗り越えて活躍するためには、モリーはこのくらいヘタレな女である必要があったのだとわかります。
ツイッターでフォロワーの人から、ラストでサムが「愛してる」と言ったのに、どうしてモリーは「同じく」と答えたのか? サムがせっかく「愛してる」と言ってくれたのだから「愛してる」と言えばいいじゃないかと思うのだがどうか、という質問が来ました。ここは確かに僕も一瞬「これでいいのかな」と思ったところです。しかしよく考えてみるといいような気がして来ます。サムは生きている間、モリーに「愛してる」と言えず「同じく」と答えてしまいます。でもこれは彼女を愛していないからではなく、照れ臭さや幸せへの恐れの気持ちがあって、素直になれなかったからです。彼は死んで幽霊となって、必死にモリーを守ろうと奮闘します。最後にはモリーもサムが自分を守ってくれていたことを知ります。モリーはサムが「同じく」としか言えなくても、ちゃんと自分を愛してくれていたことに気づくのです。このとき「同じく」は彼ら二人の間では「愛してる」よりも強い愛の言葉になるのです。だからモリーが「同じく」と言うのは、より強い愛の表現になっていると言えると思います。
以上は2時間の講義で話したことのほんの一部です。また、これらは「尾崎将也はこんなふうに分析した」ということであって、唯一の解釈ではありません。ただ、こんなふうに色々と考えて自分なりの分析をしてみることが大切なのだと思います。
〔尾崎将也公式ブログ 2013年3月25日〕